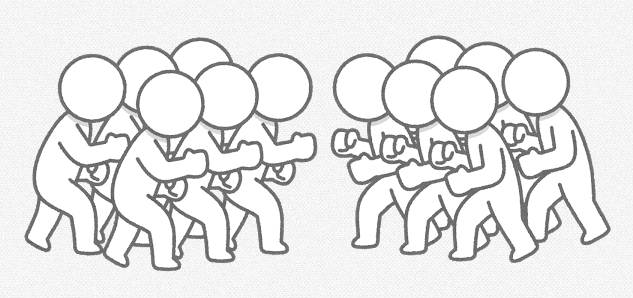【あしたのジョー全出来事79】丹下ジムの力石対策と西の「あの人は根性があるよってに」
「あしたのジョー」すべての出来事を漫画とアニメの違いを確認しながら振り返っています。
アニメ、漫画の該当箇所も書いておくので「あの場面は、何巻だっけ?アニメの第何話だっけ?」と思った時にもご活用ください。
丹下ジムは、また危険な練習方法を考え付きました。
エピソード
力石がパンチョ・レオ戦で見せたアッパーがジョーのクロスカウンターを封じる手段だと読んだ段平は、悲観的です。
力石とジョーの力量差は明らかで、ジョーが勝てるとすればクロスカウンターしかありません。
ジョーも、今度の力石戦は今までの試合と違う、勝つのか負けるのか分からない、本音を言えばあいつが怖い、と、力石の不気味さを語っています。
でもジョーと段平は、ここからの発想が違います。
段平は、力石戦ではガードを固めるしかないと考えますが、ジョーは、あくまでノーガードで行くべきだと主張します。
力石クラスの強力なアッパーには、ガードも弾き飛ばされる。ならば両手ブラリの姿勢でスウェーバックで対応したほうが有効だという理屈です。
そうなのか?
ボクシングをやったこともない私には分かりません。
ボクサーの知り合いもいません。
とにかく丹下ジムは、その作戦を採用します。
また特訓がはじまるのですが、その練習方法が…
段平と西、ふたりで同時にジョーにアッパーを出し、ジョーはスウェーバックで両方のアッパーをよけるというやり方なのです。
気を失うとバケツの水で叩き起こしてもう一度。
それでもジョーは内心、これで力石に勝てるのか不安に思っています。
減量の壮絶さが、力石の凄みを増幅させています。
少年院でも似たようなことがありました。
ジョーが通り魔トレーニングでクロスカウンターを習得すると、力石は猛牛を相手に特訓をはじめ、それを見たジョーがふさぎ込んでしまったことが。
力石徹が経験や実績でジョーを上回るボクサーであることは、周知の事実ですが、リングの外でやることもまた桁外れです。
敢闘において生涯誰にも負けることのないジョーですが、力石の勝負に対する執念は、そんなジョーをもおびやかすほどに強く、ジョーはファイターの本能でそれを察知しているのでしょう。
スウェーバックの正常な練習法↓ 美技にほれぼれ
該当箇所
コミック:8巻 はじめ~P.23
アニメ:第44話「苦闘!力石徹」~第45話「打倒!力石へのスェイバック」
コミックの掲載箇所としているのはKCコミックでのページです。
原作とアニメの相違点
丹下ジムのトレーニングは同じですが、西の様子がまったく違います。
夜中にうどんを隠れ食いしているところをジョーに見咎められ、みそっかす、男のくず、恥を知れと切り捨てられた西でしたが…
原作では、ジョーと段平が力石の試合から帰ってくると、西はひとりで縄跳びをしています。
そして、力石が勝ったと聞くと
でっしゃろな
あの人は根性があるよってに…
KCコミックあしたのジョー(8)P14 (c)高森朝雄・ちばてつや2012
と言います。
「根性があるよってに…」
あの人は強いからとか、あの人は天才だからではなく、根性があるから。
西は、自分が力石のように世界タイトルを狙うような選手になれるとも、ジョーのように観衆を熱狂させるボクサーになれるとも思っていないでしょう。
それは資質の違いです。
でも、才能では負けていても、根性でなら勝てるはず。
ボクサーとしての地位は決して追い抜くことができなくても、同じように頑張ることならできないはずがない。
才能に劣るのに努力でまで負けていてどうするのか。
ジョーと一緒にいられるという理由でボクシングの世界に入った西でしたが、このとき、こんなことを考えたのかな?と思います。
だから力石の技量についてではなく、「あの人は根性があるから」と言ったのかなと。
それを大げさに「わいは生まれ変わったで」とか宣言しないところが、またいい!
このときから西は、泣き言を言わなくなり、地道に勝ち星を積み上げていきます。
アニメにはこの場面がありません。
ふたりがジムに帰ってきてアッパーとガードの理論をリングで検証し始めたとき、西は屋根裏で寝ています。
物音で眼を覚ましますが、眠気に引っ張られてまた寝てる…
この大いに学ぶべきところのある西の変化をアニメがカットしているのは残念です。
この西の名言「あの人は根性があるよってに」は、ほとんど取り上げられるがなく、これからも注目されることはないでしょう。
でも私は、なにかあるたびに思い出しています。
「あの人は根性があるよってに」